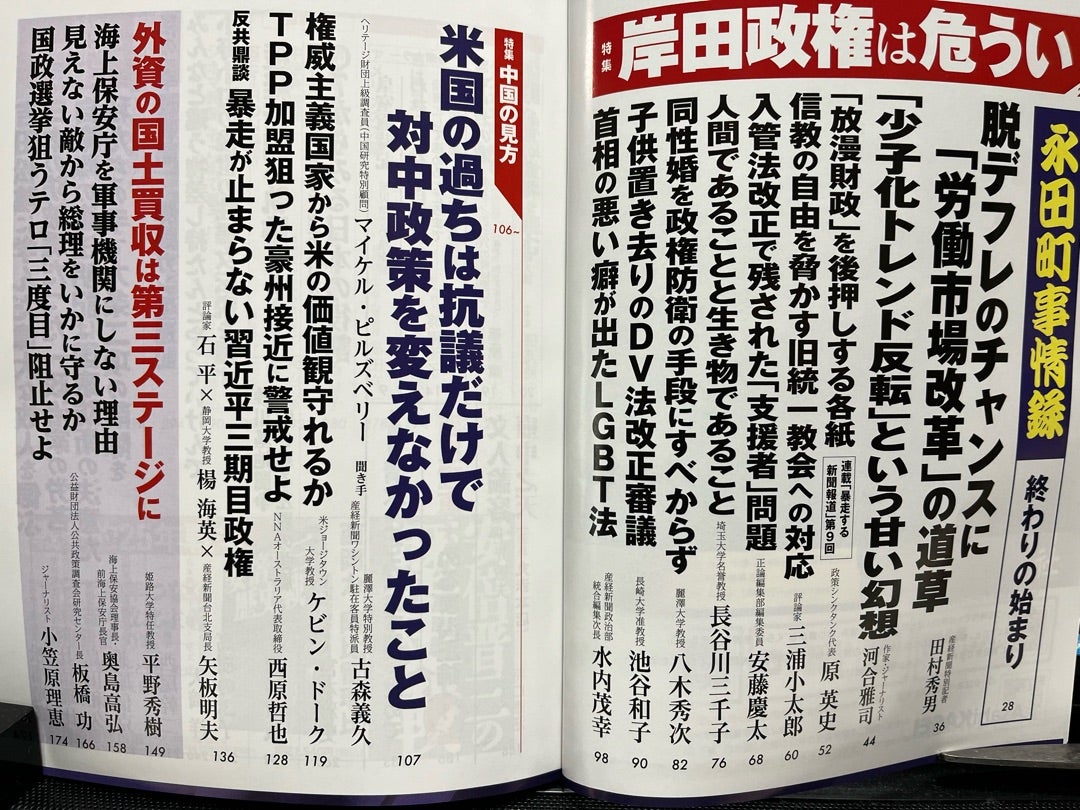以下は昨日発売された月刊誌「正論」に掲載された長谷川三千子埼玉大学名誉教授の論文からである。
日本国民のみならず世界中の人たちが必読。
特にダボス会議を主催している者、これに嬉々として集っている、何度生まれ変わっても使い切れないお金だけは持っているが似非モラリストで強欲な大バカ者たち、米国民主党の関係者、バイデン夫妻、駐日米国大使エマニュエル等は、刮目して読まなければならない。
見出し以外の文中強調は私。
人間であることと生き物であること
人間も生き物だーこの単純な事実を、われわれ人間はときどき忘れてしまひます。
無理もありません。
たしかに人間は他の生き物と比べて、とんでもなく特異な生き物です。
鳥でもないのに、空を飛びまはり、月にまで行ってしまふ。
魚でもないのに大海原を往来し深海の底までもぐることができる。
そんなすばらしい能力に恵まれた人間を「生き物」呼ばはりするのは人間に対する侮辱だ、と感じる人がゐても不思議ではありません。
しかし、さうした特異な生き物であるからこそ、われわれは自分が生き物だといふ事実を忘れてはならない。
少し理屈っぽい言ひ方をすれば、われわれ人類は、地球上の他のあらゆる生物と共に三十数億年におよぶ生命の歴史の最新ページを生きてゐるわけであって、その歴史をしっかりとふり返ることなしには、子供たちに命の大切さを教へる教育を、などと言ってみても絵空事にしかならない。
また、昨今しきりに議論されてゐる、いはゆる同性婚の法制化は是か非かといふ問題についても、われわれ人類を生み出してきた生命の歴史の根本を忘れては、トンチンカンな議論に終はってしまひかねないのです。
五億年に及ぶ有性生殖の伝統
いまわれわれは、動物や植物や細菌、その他の生き物にみちみちた世界に住んでゐて、それをあたり前だと思ってゐますが、そもそもこの地球上に生命が誕生したといふこと自体、文字通り奇蹟的な出来事だったのです。
太陽のまはりをめぐる惑星のなかでも、われわれの住む地球は、太陽からの距離がちやうどよい具合で、炭素や水や窒素などから有機化合物が合成されるための最適の条件が整ってゐた、といふ話はよく耳にします。
しかしそれだけでは生命は誕生しない。
そこから「自己複製の可能な」蛋白質が形成されてはじめて生命が誕生したと言へるのだけれども、それは「何億分のIかの確率でしか起こらない化学反応」であった、と或る古代生物学者は語ってゐます。
つまりわれわれ人間も、その奇蹟的なただ一回かぎりの出来事の結果として今ここにゐる、といふ点では、ゾウリムシともペンギンともかはりがない。
他のすべての生物と共通の〈生命の歴史〉をわれわれは生きてゐるのです。
その歴史は決して平穏なものでも平板なものでもありませんでした。
ごく初期には、大量に発生した藍藻による光合成の結果、大気の組成がすっかり変化して、酸素に耐へられない古い細菌たちは海底や火山の底にもぐるほかなくなりましたし、その後にも、隕石の衝突その他の原因による、いはゆる大量絶滅が何度も起ってゐたらしい。
古代生物学者たちはその痕跡をいくつもの地層から発見してゐます。
しかし、それで地球上の生命がとだえてしまふことにはならず、かへってそのつど、新たな生物群があらはれては繁栄し始める、といふことが繰り返されてきました。
かうした生命の歴史を眺めてゐると、(文字通りの同語反復になりますが)これこそが「生命力」といふものなのだなあ、といふ感想がうかんできます。
ことにそれが強く感じられるのは、その歴史が、つねに新しくより複雑に変化し、多様化していくーいはゆる「進化」の歴史として展開してゆくのを見る時です。
この「進化」といふことがなかったら、われわれ人間がこの地球上に存在することはなかった。
われわれはまさに進化の申し子なのです。
では、進化の歴史はどんなふうに展開していったのか?
そこにはいくつかの重要な節目のあったことが指摘されてゐるのですが、そのなかでも、進化の歩みを大いに加速したと言はれるのが、およそ五億年前に始まったとされる有性生殖でした。 有性生殖とはすなはち、メスとオスとが一緒になって子供をこしらへるといふ、われわれにとっては一番おなじみの、生物の増殖方法ですが、実はこれが、従来の無性生殖とは根本的に異なる革命的な新方式だったのです。
性の区別のない単細胞生物は、栄養が充分にゆきわたってゐると細胞分裂をおこして二個の個体になります。
その時、どちらの個体もそっくりそのままもとの遺伝子の組み合はせを持ってゐるーいはゆるクローンです。
このやうな増え方だと、細胞分裂中の遺伝子の転写ミスなどが起らないかぎり、何代をへても同じ遺伝子の組み合はせをもちっづけることになります。
これに対して、有性生殖を行ふ生物は。二組になった自分の遺伝子の一組だけをのせた配偶子を作り、別の相手の配偶子と合体させて新しい個体を作り上げる。
この方式だと次の世代はかならず両親のどちらとも違った遺伝子の組み合はせをもっことになります。
敢へて言へば、有性生殖の一回ごとに、変化と多様化といふ「進化」のごく小さな歩みが起ってゐるといふことになるわけであって、生物学者たちがこの革命的な新機軸を、進化の歴史上の大事件と見てゐるのも当然のこととうなづけます。
ただしこの有性生殖といふ新方式は、それまでは存在しなかった厄介な問題をもたらします。
すなはち、メスとオスとが出会はなければならない、といふ問題です。
それまでの単性生殖では、その個体自身の条件さへととのってゐれば、いっでもどこでも増殖できる。
まさに「おひとりさま増殖」の気楽さです。
ところが有性生殖はかならず相手を必要とする。
それも、どんな相手でも良いわけではなく、メスならオス、オスならメスが相手でなければならない。
といふのも両者の提供する配偶子は本質的に異なつてゐて発生に必要な栄養をそなへた卵と、動きまはることはできるけれども栄養のストックがない精子といふ二種類に分かれてゐる。
そして、この二種類が結合しないと新個体の発生は起らないのです。
同性婚裁判を考える
いまわれわれが地球上に見かける有性生物は、オスとメスが出会はなければならぬといふこの厄介な問題に、さまざまな仕方で対処してゐます。
南洋の島に住むフウチョウたちのやうに、美しい羽と踊りでオスがメスを誘う鳥もゐれば、オオツノヒツジのやうにオス達が力くらべをしてメスを獲得するといふ動物も多く見られます。
あるいはまた、一種の集団結婚といった方策をとる生物もゐる。
たとへば、夏の間は一尾づつ清流の縄張りに陣取ってゐた鮎も、秋になると群をなして川を下ります。
河囗にたどりつくとメスは小石の間に卵を産み、オスたちはそこに精子をまいて受精させ、その共同作業が完了すると、鮎はその短い一生を終へる。
そしてそこで孵った子供たちは、海の浅瀬でたっぷり食べて育ってから、春にはまた川上をめざして遡行してゆくのです。
先ほどはいささか他人事めいた言ひ方で「生命力」などといふ言葉を持ち出しましたが、その内側に目をこらせば、そこにはかうした周到な行動プログラムと、それを全力で実現する生き物たちの奮闘がある。
つくづくと、有性生殖とは安易なものではないのだ、と思ひ知らされます。
ならば、われわれ人間の場合はどうなのか?
少なくとも、鮎たちを律しているやうな、有無を言わせぬ行動プログラムといったものはわれわれの内には見あたらない。
そんなものに律せられてゐたら、人間として生きていくことはたうてい不可能です。
しかし、有性生殖の難しさといふことを考へるとわれわれにも何かそれを支へてくれるものは必要なはづです。
おそらく、われわれがいま「結婚」の制度として有してゐるものが、そのはたらきをしてきたと言へるでせう。
いつ誰が定めたのでもなく、その形態や細かい取り決めはさまざまであるにしても、いつの時代のどの民族にもなんらかの形で存在してきた慣習・制度である結婚-これこそが、有性生殖といふ困難をのりこえて、われわれ人間の繁殖を支へてくれてきたシステムだと考へられるのです。
では、その結婚といふ制度から〈男性と女性の〉といふことを取りはらつてしまつたら、はたしてそれは結婚と言へるのかどうか?
それが問はれてゐるのが、いはゆる「同性婚」をめぐつての裁判です。
たとへば今年五月三十日に名古屋地方裁判所で判決の出た裁判は、原告の男性二名が「同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は憲法二四条及び一四条一項に違反するにもかかはらず」、国がそれを改廃しないままにしてゐたので不利益をかうむった、として国に慰謝料を請求して起こした裁判です。
そこでは、原告の請求を棄却するといふ判決が出たのですが、注目すべきところは、そこで同性婚そのものについてどんな見解が示されたのか、といふ点です。
それについて、この判決文では、まづ憲法二四条一項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」について、これはもともと男性と女性との結婚を念頭において定められた条文なのだから、現行の民法、戸籍法も憲法違反ではないとして、次のやうに語ってゐます。
「人類は、男女の結合関係を営み、種の保存を図ってきたところ、婚姻制度は、この関係を規範によって統制するために生まれた。」
さらに、時代や地域によって婚姻制度の形はさまざまだけれども、「男女の生活共同体として、その間に生まれた子の保護・育成、分業的共同生活の維持など」の役割をになって「家族の中核を形成するものと捉えられてきた」と述べてゐるのです。
ここには、有性生物の一員としての人類にとって〈男女の結婚〉といふ制度がいかに大切なものであるかが過不足なく語られてゐます。
そして、それによれば結論は明白です。
同性の結婚を人類の婚姻制度のうちに認めることは不可能だ、といふことになります。
ところが、憲法二四条二瑣に言ふ、「婚姻及び家族に関するその他の事項」に関しての「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」といふ文言を解説するあたりから、判決文はにはかに迷走を始めます。
実は、その責任はこの憲法自体にあるとも言へるので、まさに「婚姻」といふ、生物としての人間のあり方の根本に即して考へなければならない問題に、近代の発明品である、(意識と意志の主体としての)「個人」などといふ言葉を持ち込んでしまったら、話は大混乱に陥ってしまふ。
そんなことも知らない人問たちの起草した憲法をもとに論じてゐれば、話が迷走するのは当然とも言へます。
しかしそれにしても、男女の組み合はせとして結婚を考へるのは「伝統的な家族観」であって、時代とともに、それが「唯一絶対のものであるというわけではなくなっている」といふ言ひ方は、この書き手が「婚姻の本質」を全く心得てゐないことを暴露してゐます。
その「伝統」は、人類の歴史よりはるかに長い、五億年の長さを持った伝統なのです。
あの「人類は、男女の結合関係を営み、種の保続を図ってきた」といふ堂々たる宣言はどこに消えてしまったのか?
少なくとも、あの言葉には、われわれ自身を、地球上の三十数億年におよぶ生命の歴史の1コマをになふ一員として捉へる誇りと責任が感じられました。
そして、その自覚こそが、かうした問題を正しく考へてゆくために不可欠のことなのです。
本当の「理解」の増進を!
その意味で是非最後に付け加へておきたいことがあります。
つい最近、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」なるものが、国会で可決成立しました。
中身の詳細については、いはば左右両側から多くの批判がありますが、いまここで問題にしたいのは、その「理解」といふことの意味そのものです。
マスコミはしばしば「理解」といふことを、気の毒な人々への同情と共感といふ意味で使ひます。
しかし、そんなものは本当の理解ではない。
必要なのは、事柄そのものを根本の枠組から理解すること。
そしてわれわれ人間は、つねに〈人間であること〉と〈生き物であること〉の難しいバランスを取りながら生きてゐる存在なのだと知ることー大切なのはこれだけです。
そのやうな本当の意味での理解が増進すれば、トンチンカンな議論が世にはびこることはなくなるはずなのです。